化学工学技士(基礎)は、学生や若手エンジニアが最初に挑戦しやすい資格です。
2025年度からは上位資格に進むための必須ステップにもなり、これからますます重要度が高まっていきます。
ただし「独学で受かるの?」「どの参考書を使えばいい?」という悩みを持つ人は少なくありません。結論から言うと、良書+過去問を正しく使えば、独学でも十分に合格可能です。
本記事では、
- 試験の位置づけと最新データ
- 独学でも突破できるロードマップ
- 合格者が実際に使った参考書と過去問戦略
を体系的にまとめました。「化学工学技士(基礎)をどう攻略すればいいか?」という疑問は、この記事を読めばすべて解決します。
👉 さあ、ここから合格への最短ルートを一緒に描いていきましょう!
-
化学工学技士基礎とは?
そもそも、化学工学技士(基礎)とはどんな資格なのか。結論から言うと、 化学工学技士(基礎)とは、化学工学の基礎力(計算+用語)を測る“入口”資格です。 直近 2024年度は受験者253名・合格191名(合格率≒75%) と現実的な難易度で、独学でも十分に合格を狙えます。さらに 2025年度からは上位の「化学工学技士」を受けるための必須要件 になり、取得価値が一段と上がりました。 SCEJ公益社団法人 化学工学会
試験の位置づけ(どんな資格?)
- 主催・認定:公益社団法人 化学工学会(SCEJ)
- 役割:化学工学の基礎知識を修得していることを学会が認定するエントリー資格であり、上位には「化学工学技士」「上席化学工学技士」があります。
- 重要トピック(2025年度以降):上位の「化学工学技士」試験の第一部(基礎相当)を廃止し、受験要件を「化学工学技士(基礎)」保有者に限定されました。つまり、基礎を取っておくことが、上位資格への“必須ステップ”になりました。
出題範囲と試験形式(何が出る?)
- 形式:筆記(択一式が主体+一部記述)
- 内容:
- 計算問題(基礎的な計算力)
- 用語説明(基礎用語の理解)
- 範囲:単位・次元/量論、熱力学、流動、伝熱、分離、反応工学、粉体、プロセス制御。
※いずれも公式ページに明記されています。 公益社団法人 化学工学会
受験者数・合格率(直近データで把握)
- 2024年度:受験者253名/合格者191名(全国15会場・試験日:2024年9月28日)
→ 合格率は約75% と独学でも十分“狙える”試験です。 - 過去データ(制度解説資料):2011〜2018年度の受験者数推移・合格率推移グラフ、および合格基準「60点以上」の記載があります。基礎は立ち上げ以降、学生・若手の入口資格として定着してきました。 公益社団法人 化学工学会
認定の有効期間(いつまで有効?)
- 化学工学技士(基礎)の認定期間は8年間。8年経過で自動失効です。→ 基礎の有効期間中に、上位の「化学工学技士」受験を検討しておくのが賢い動きだと言えます。
ひとことで言うと…
- “基礎”は合格実績も出ていて、独学でも十分届く
- 今後は「化学工学技士」への必須パスポート
- 出題は“計算+用語”&王道分野中心。
だからこそ 「限られた良書+過去問」 に的を絞れば、 短期でも積み上げやすい 試験です!!
-
独学ロードマップ
まず前提として、 化学工学技士(基礎)は決して「楽勝の資格」ではありません。たしかに合格率は高く、資格の難易度としてはそこまで高くありません。しかし、たとえどんな資格であっても、”楽勝に受かる”なんてものはありません。 大学で一通り学んだ人でも「公式テキストを眺めただけ」では合格点に届きにくいのが実情です。
だからこそ大切なのは、全体像を最初に掴み、重点分野に時間を配分しながら段階的に仕上げること!!
ここでは、堅実に取り組む人のための【1年プラン】と、試験直前でもまだ間に合う【2か月プラン】の両方をご紹介します。
1年かけて合格を狙う堅実プラン
「時間をかけて確実に実力をつけたい!」という方はこちら。
1年をかけて学べば、基礎知識ゼロからでも合格レベルまで到達可能です。
全体像を掴んだ上で、伝熱・流体を同時並行、分離・反応にしっかり時間を割くのが鉄則です。直前期に粉体・プロセス制御をまとめれば、バランスよく得点できる盤石な仕上がりになります。
前半(1〜4か月):基礎を固める
- 単位・次元・量論を最優先で学ぶ
→ すべての計算問題の土台。ここを甘くすると後半でつまずきます。 - 伝熱工学と流体工学を同時並行で学習
→ 熱移動と流体挙動は公式や考え方がリンクしているため、同時に進めると理解が深まりやすいです。 - 到達レベル:基礎問題を解答解説を見ながら“自力で再現できる”段階。
中盤(5〜8か月):時間をかけて分離・反応を攻略
- 分離工学(蒸留・吸収・抽出)と反応工学(転化率・速度式)は、試験で頻出かつ理解に時間がかかる分野。
- 1テーマごとに「概念 → 計算例題 → 過去問対応」という流れで学習を積み上げます。
- 到達レベル:過去問で6割程度を安定して得点できること。
終盤(9〜11か月):総合演習で弱点を潰す
- 過去問を“年度別”に解いて、本番の時間配分を体感。
- 苦手分野を参考書や問題集に戻って徹底復習。
- 到達レベル:過去問で常に7割以上を取れる状態。
直前期(12か月目):最終調整
- 粉体工学・プロセス制御は直前期で十分。試験合格レベルに到達するまでの内容量は少ない。頻出度は低いが、落とすと合格点に届かない可能性があるので対策必須。
- 暗記系(用語・定義)を一気に総仕上げ。
- 過去問は“論点別”に整理し直し、典型問題を反復演習。
👉 1年かけて学べば、基礎力・計算力・本番力をバランスよく育てられるため、初学者でも十分に合格可能です。
まだ間に合う!2か月追い込みプラン
「試験まで時間がない…」という方のために、短期集中型の戦略も示します。
ただし、2か月で合格を狙う場合は“完璧”ではなく“合格点確保”が目的です。
そのため、重要分野・頻出分野に絞った”60点”を確実に目指すべきです。
ニッチな分野は余裕が出てきてから取り組みましょう!!
Week 1〜2:過去問から逆算
- 過去問1年分を解いて苦手分野を可視化。
- 基礎の「単位・次元・量論」を確認。
Week 3〜4:重点分野の集中攻略
- 得点配分の大きい分離工学・反応工学を徹底演習。
- 並行して伝熱・流体を“公式暗記+典型問題演習”で固める。
Week 5〜6:過去問シャワー学習
- 過去3〜4年分を繰り返し解き、頻出パターンを“暗記レベル”に落とす。
- 粉体・プロセス制御はここで最低限仕上げる。
直前1〜2週間:総仕上げ
- 模擬試験形式で時間を計り、本番シミュレーション。
- 間違えた問題だけをノート化して、試験前日まで見直し。
👉 このプランでも50〜70時間の学習を確保すれば、合格ライン突破は十分現実的です。
ひとことで言うと…
-
- 1年プラン → 知識ゼロからでも堅実に合格可能。
- 2か月プラン → 苦手分野を切り捨てず、出題頻度の高い分野から潰していくのがカギ。
大切なのは「全体像を掴み、出題頻度に応じて勉強時間を配分する」こと。
この戦略さえ意識すれば、独学でも合格への道は開けます。
-
過去問の使い方
化学工学技士基礎に合格する最大の近道は、参考書と過去問を繰り返すこと。 1回解くだけでは不十分で、「参考書 → 過去問 → 参考書 → 過去問」と何度も往復しながら理解を深めることが合格率を大きく左右します。
参考書と過去問の“往復学習”が鉄則
- 過去問を解いてみると、「あ、この問題、参考書の例題とほぼ同じだな」と感じることがあります。
- 実際、出題形式は変わっても、使う公式や考え方は同じことが多いのです。
- 重要なのは「数値や問い方が変わっても、同じ解法ができる」状態まで持っていくこと。
👉 つまり、過去問は「理解の浅さをあぶり出すチェックリスト」と捉えましょう。
過去問は“印刷して、眺めるだけ”でも効果あり
- 「まだ解けないから…」と過去問を封印するのはNG。
- まずは全部印刷して、常に手元に置いておくことをおすすめします。
- 電車の中やちょっとした休憩時間に眺めるだけでも、「どんな形式で問われるか」を自然に覚えてしまいます。
👉 解けなくてもいい、まず触れることが学習効率を上げる第一歩です。
過去問は【タテ×ヨコ】で攻略する
タテ(年度別で解く)
- 本番形式を意識する練習になります。
- 時間配分・総合力チェックに有効。
ヨコ(分野別で解く)
- 「伝熱だけ」「流体だけ」と切り分けて学習すると、弱点が一目でわかる。
- 苦手分野を集中対策できるため、効率的に点数を伸ばせます。
👉 最強の戦略は、タテで模試感覚 → ヨコで弱点克服の両輪学習です。
分野別整理ファイル(PDF)を活用しよう
この記事では、過去問を分野ごとに仕分けした整理用PDFを準備しました。完全オリジナルです!!自分でコピーして仕分けるのも有効ですが、最初から分野別になっていると学習効率が段違いです。
ひとことで言うと…過去問は「解く」だけじゃなく「使い込む」こと
- 参考書と過去問を往復して“本質理解”に到達する
- 解けなくてもまず印刷・眺める
- タテ(年度別)×ヨコ(分野別)の両輪で攻略する
この3ステップを守れば、過去問が単なる問題集から「合格の教科書」に進化します。
合格者の多くが口を揃えて言うのは「過去問をどれだけ使い倒したか」。
あなたも、ぜひ今日から「過去問シャワー学習」を始めてください。
-
合格に効く参考書セレクト
まず押さえておきたい「参考書選びのトレードオフ」!!
参考書には大きく分けて2つの軸があります。
- 読みやすさ・解説の丁寧さ
- 内容の深さ・演習量
この2つは往々にしてトレードオフの関係にあり、「解説はやさしいけど浅い」本と、「演習や内容は濃いけど解説が少ない」本に分かれる傾向があります。
👉 したがって、1冊で完璧を目指すのではなく、全体像をつかむ本+補強する本を組み合わせるのが王道です。
A. 全体像をつかむための3冊(基軸)
- ベーシック化学工学 増補版(橋本健治)
- 初学者が概念を理解するのに最適。
- 丁寧な説明とシンプルな例題で「化学工学ってこういう学問なんだ」と入門するのにうってつけ。
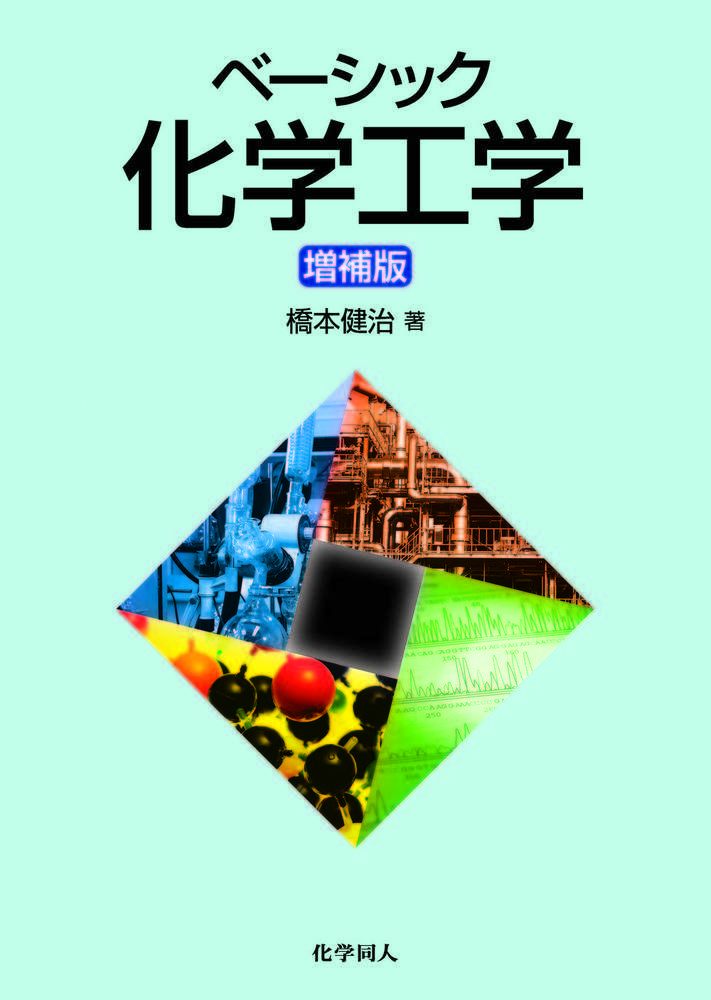
- 現代化学工学(橋本健治)
- 解説・読みやすさ・内容の深さのバランスが最も良い一冊。
- 「これ一冊を軸にすれば、基礎→応用まで合格レベルをカバー可能」。
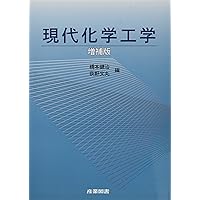
- 化学工学 解説と演習(多田豊)
- 解説は簡潔で淡泊だが、演習問題は豊富でレベルが高い。
- 「計算力を鍛える」ために後半で取り組むのがおすすめ。

👉 管理人のおすすめ:”現代化学工学”+”解説と演習”を併用すると、読みやすさと深さのバランスが取れます。
B. 分野別で補強すべき本
1. 伝熱工学・流体工学
- 輸送現象(水科)
→ 伝熱・流動を一体で理解できる名著。
- JSMEテキストシリーズ(伝熱/流動)
→ 定番の教科書。網羅性が高く、辞書的に使える。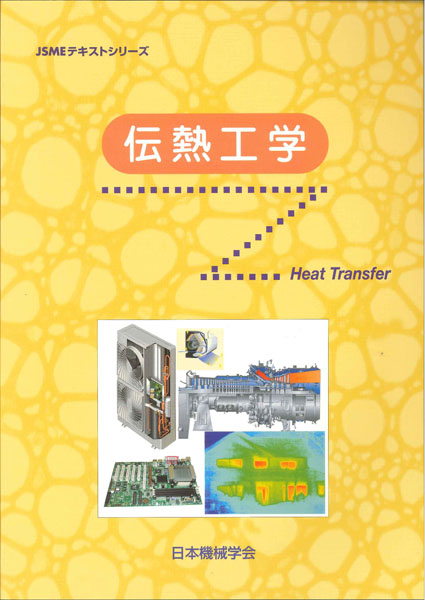
- 図解 伝熱工学の学び方(北山)
→ 図解多めで理解しやすい。特に伝熱が苦手な人におすすめ。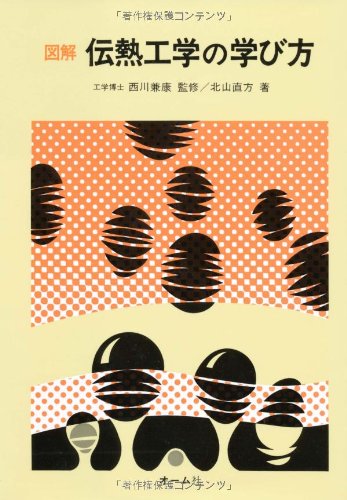
2. 反応工学
- 反応工学(橋本健治)
→ 「神」と呼ばれるほどわかりやすく、本試験でも必携レベル。反応工学といえば【橋本健治】!! - (補助)反応工学(草壁)
→ 橋本に比べると内容の深さ・演習量は劣るが、解説は非常に丁寧である。
3. 分離工学
- 蒸留技術大全(大江)
→ 難度は高いが、分離工学の本質をつかむ一冊。 - 絵解き 蒸留技術 基礎の基礎(大江/廃版)
→ 廃版になってしまった本。図書館で見つけたら必ず読んでほしい幻の名著。”蒸留技術大全”に比べて、非常に分かりやすく理解しやすい。蒸留理解の最強本。蒸留といえば【大江先生】!!!
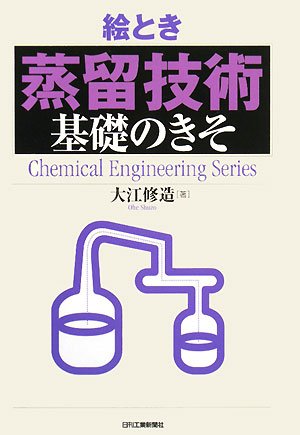
※分離工学は枝分かれが多いですが、蒸留を深掘りすれば全体が見えるため、蒸留から入るのがおすすめです。
4. 熱力学
- アトキンス物理化学(上)
→ 王道。ただし難易度は高い。英語版なら解答付き。
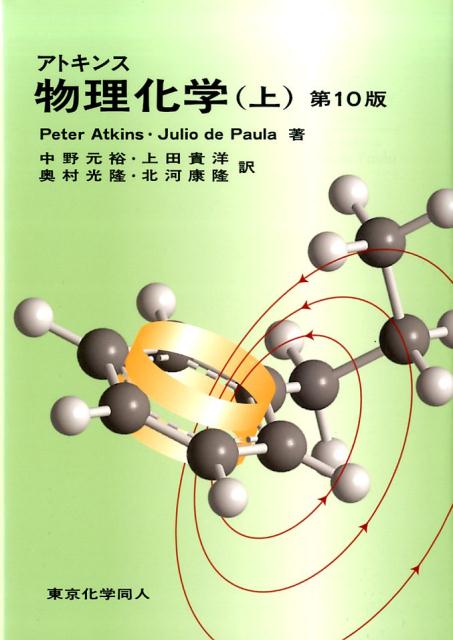
- 右脳式 演習で学ぶ物理化学(熱力学と反応速度式)
→ 初学者にやさしい“穴場”本。演習を通して熱力学を体感的に理解できる。
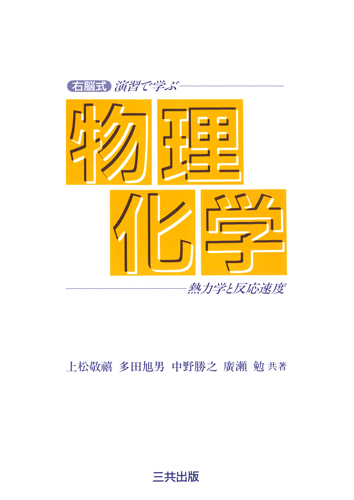
- 化学熱力学入門 みえる!つかえる!(由井)
→ ビジュアル重視で学べる入門書。最初の一冊としても有効。

ひとことで言うと…
- 全体像把握は「現代化学工学」が最適解
- 理解しやすさ重視なら「ベーシック化学工学」から
- 演習力強化は「解説と演習」
- 分野ごとの補強は、伝熱=水科/JSME、反応=橋本、分離=大江、熱力学=アトキンス
この組み合わせで「基礎理解 → 計算力強化 → 分野深掘り」という盤石の流れが作れます。
特に反応工学と蒸留は落とし穴になりやすいため、意識的に時間を割くのがおすすめです。
-
まとめ
化学工学技士(基礎)は、受験者数・合格率のデータを見ても分かる通り、正しい方法で学べば独学でも十分に合格を狙える資格です。
合格戦略の軸はシンプル。
- 全体像をつかむ良書を1冊
- 計算力を伸ばす問題集や演習書
- 過去問をタテ(年度別)×ヨコ(分野別)で繰り返す
この3ステップを押さえるだけで、短期間でも得点力を大きく伸ばせます。
さらに、この資格は2025年度から上位資格「化学工学技士」への必須ステップとなりました。 つまり、今取っておくことが将来のキャリア形成に直結するのです。
👉 「参考書+過去問」の組み合わせで、合格は十分可能です。 あなたの努力は必ず形になります。ぜひ一歩を踏み出して、次のキャリアにつながる合格を勝ち取りましょう!
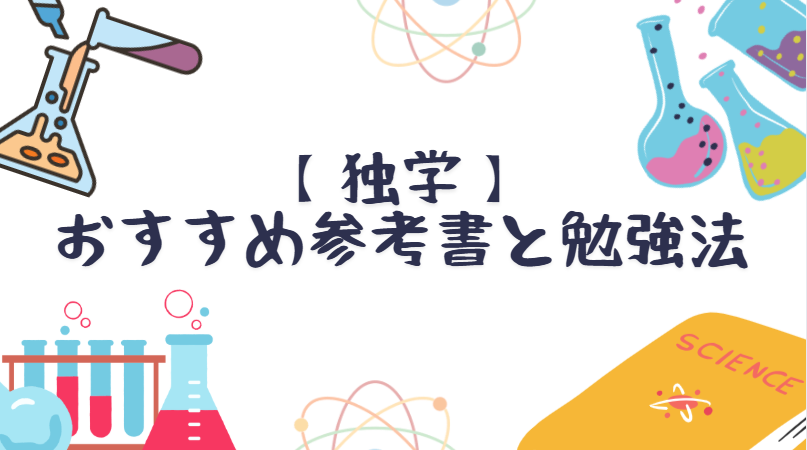
コメント